製造基準が法律で定められていない加工品の作り方
社会人向け加工食品専門学校ピクルスアカデミー
加工食品を製造する場合、当然ですが「製造許可」が必要になります。
製造許可はどの加工品を作るのかによって取得する許可が決まっています。
例えばパンやジャムなどを作りたいのであれば「菓子製造業」、飲み物を作りたいのであれば「清涼飲料水製造業」、冷凍食品を作りたいのであれば「冷凍食品製造業」といったように細かく細分化されているのです。
これらの製造業は何故ここまで細分化されているかと言うと、各製造業でカバーされている食品群の殺菌方法や衛生管理の方法が違うからです。
例えば漬物を作る場合は「漬物製造業」を取得しなければならないのですが、漬物の場合は塩分を何%にして、殺菌はこのようにしてくださいというのが決まっていたり、冷凍食品製造業の場合は-15度以下の冷凍室、保管室を用意しなければならないなど、製造業によってバラバラなのです。
しかし、加工食品の種類というのは無数にあるので、全ての食品を個別に食品衛生法でカバーすることは現実的に不可能です。
言い換えれば、「製造基準が定められていない加工食品が世の中には沢山ある」という事です。
例えばオイル漬け。
オイルサーディンや牡蠣のオイル漬けなどは製造基準がありません。

何故かというと、微生物は水分がないと増殖ができないので、「オイル漬けの食品は基本的には腐敗しない」という大前提があるので製造基準がそもそも存在しないのです。
では加熱殺菌などはしなくて良いのか?と言うと、それは全く違います。
今お話ししているのは、「オイル漬けの製造基準がない」というだけで、殺菌は必ずしなければなりません。
製造基準とは「中心温度が何度になるまで加熱をして、そこから何分以上加熱しろ」と定められているものです。
その基準が定められていない加工食品が沢山ある、というだけで加熱殺菌は必ずしなければならないのです。
では「そういった食品は何を基準にして加熱殺菌をすればよいのか?」というと、その加工食品がどのような形態で販売されるのかによって変わるのです。
例えばオイル漬けの商品を瓶や缶詰に入れて販売するのであれば「密封包装食品製造業」の製造基準に従うことになります。
これ、実は「缶詰又は瓶詰食品製造業」という許可があったのですが、令和3年の法改正で廃止をされ今は「密封包装食品製造業」に再編されたのです。
食品衛生法は技術の進歩や時代の流れとともに結構な頻度で法改正が行われます。
この情報をきちんとキャッチしておかないと、今まで大丈夫だったものが知らない間に「違法」となってしまうこともあるのです。
話がそれましたが、オイル漬けを「瓶」でつくる場合は「密封包装食品製造業」の製造基準に従い、その食品内のpHとAwの数値によって殺菌温度と時間が明確に定められています。
例えばpH4.0以下であれば「中心部の温度を65℃で10分間加熱する、又はこれと同等以上の効力を有する方法で行うこと」というような感じです。
マヨネーズを作る場合は卵黄を61℃で3.5分以上加熱しなければならないなど定められています。
これはサルモネラ菌の死滅条件が61℃で3.5分だからです。
レトルト食品の場合は「120℃で4分以上」と定められているのは、ボツリヌス菌の死滅条件です。
このように「何度で何分加熱」というのは微生物の生育限界環境を元に厳密に決められているので、適当に加熱時間や温度を自分勝手に決めてはダメなのです。
何故今回このようなお話しをしたかと言うと、昨日受講生から「細菌検査を何度やってもカビが発生して失敗する」という相談が届いたからです。
こんなのは原因は一つしかありません。
法で定められた加熱殺菌条件を守ってないからです。
この受講生にどんな加熱殺菌をしているかと聞いたら、案の定私が教えた加熱殺菌方法を全く守っておらず、適当な加熱温度と時間で処理をしていました。
「もう一度動画とテキストを読み直してその通りにやってください。それをすればその現象は100%二度と発生しないので安心してください。」
とだけお伝えしました。
世の中にはネットに出ている情報を鵜呑みにした無責任な製造者が、適当に加熱殺菌処理をして商品の製造をして販売しています。
スーパーに並んでいるような商品でそういったものは絶対に並んでいません。
それは取引の際に商品企画書の提示が求められ、商品の安全性の担保の確認が確実に入るからです。
しかし、田舎の道の駅や直売所ではそれがスルーされる事があります。
特に個人店のオリジナル商品などは店主しかチェックをしないので、自分が売りたいと思えば売れてしまう状況なのです。
よくあるのが個人店のパン屋の店主がつくってるジャム。
うちの受講生でも一番多いのがこのパターンです。
そんな状況に危機感や恐怖感を覚えてこの講座を受講される方はまだマシなのですが、そんなこと何とも思っていない事業者も多数いらっしゃいます。
ではどうやればそんな商品の見分けがつくと思いますか?
正解は「見分けはつかない」です。
現行の法律ではこの商品がどの細菌検査をクリアしているのか、なんて書く必要がないからです。
製造者のモラルに任せるしかない、というのが現状です。
うちの受講生には徹底的に細菌について学んでもらうので、絶対にそんな商品は作らせませんが、食中毒なんか起こした日には事業なんて一発で終わりますからね。
ほんとみなさんも注意してくださいね。
それでは!

今日はちょっと驚いたというか、うれしくて感動したお話をします。 これ今朝なんですが、うちは今日が仕事始めでした。 うちの商品はサンドイッチやフルーツサンドなど殆どが前日製造なので、昨日作っておかないと今日売るものがありません。 しかし、スタッフには正月休みはゆっくりしてもらいたいと...

今朝こんなお問い合わせを頂きました。 おはようございます 質問です。萩野菜はブランド野菜だと思うのですが、自分で作っている他県の野菜でも萩野菜のピクルスとして販売出来るのでしょうか? それに対するお返事がこうです。 明けましておめでとうございます。 またお問い合わせ頂きありがとうございます。...

年も明けうちのお店は月曜日からお店を開店する予定です。 皆様もその辺りから動き出すのではないでしょうか?? 今年もいい一年になると良いですね。 さて、今日は田舎で起業するとこについてお話ししますね。 私が起業した場所は山口県萩市という人口4万人の四方を山と海に囲まれた俗にいう...

今年最後の投稿です! 先日の東京講座を受講されたOさんは現在飲食店にお勤めなのですが、年内で閉店する為、次は自分で加工品製造に取り組みたいとの事で受講をされました。 それでは詳しく見てみましょう。 【当プログラムを受講したい目的】 現在飲食店勤務。地域の無農薬栽培田畑で援...

この前マヨネーズの作り方を皆さんに送りましたが、あれで実際にマヨネーズは作れますが商品として販売する際に食品表示の名称に「マヨネーズ」と書いちゃダメですよ? 理由はわかりますか? それはその商品の製法が「JAS規格」を遵守しているかどうかで変わるからです。 「JAS規格」 み...

昨日28日、今年最後のアカデミーが終了致しました! 今回は前日にどうしても明日受けたいとお申し込みをされた方がいらっしゃり、理由を聞くと「現在自分が作って販売しているピクルスに問題が生じたのでその原因と解決方法を至急知りたい」とかなり切羽詰まった状態でした。 事前にどんな...
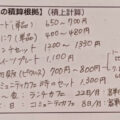
先日とある受講生から事業計画書が送られてきました。 この方はこれからカフェの開業を目指しているのですが、地元の創業支援センターや開業の手助けをしている所に足を運び着々と準備をしておられます。 進捗状況をメールで教えてもらっていたのですが、事業計画所を作成するようにと支援センターに言われて...

※今回の文章はちょっと長いです もうすぐ2ヶ月のフォロー期間が終了する受講生Sさんから進捗のご報告を頂きました。 Sさんは社会になかなか馴染めないご子息がいらっしゃり、その社会復帰のきっかけづくりをしたいとカフェの開業を目指しておられます。 受講前のヒアリングシートにはこのように書...

今日上加工品製造プログラムをお申し込みされた方はラー油を個人で直製造をしているそうなのですが、他の調味料も作ってみたいという希望がありました。 今は出張料理人をされており、知り合いの飲食店が使ってない時間帯を借りて加工品や料理の仕込みをしているそうなのですが、今後独自の加工場を設けてきちんと製...

こんにちは! 今日12月21日は私の誕生日なんですが、家族は覚えているのかドキドキしています。 去年完全に忘れられていたので(笑) さてそんな話はどうでも良いとして、18日に受講された36期生の方々から感想が届きましたのでご紹介いたします! 四国から参加のYさ...

今日は明日開催の山口講座のオンライン授業。 朝からしゃべりっぱなしで声がガラガラです(笑) 皆さんうんうんと頷きながら頑張って学ばれていました。 テキストが80Pもあるので、要点を押さえて話さないと聞いてられませんからね。 という事で今日は32期生のKさんから感想が届いたので...

昨日、卒業生のTさんからこんなお問い合わせを頂きました。 椋木先生、こんにちは。 教えていただきたいことがございます。 博多大丸での催事に出店してみないかと、鹿児島特産品協会から案内をいただきました。 催事のことは何もわからず、準備などのイメージがつきません。 相談にのっ...

丁度1年前に受講された上原さんは福岡県でいちご「あまおう」の農家をされているご夫婦です。 その奥様から商品が完成したとのご連絡を頂いたので、せっかくなので皆さまにご紹介いたします。 当時の上原さんの記事はこちらです。 以下頂いたメールです。 ご無沙汰しております。 ...

怒涛の東京講座、本日無事終了いたしましたー! 今回もフルマックスで講義をしてきたのでヘトヘトです。 20日は山口講座、こちらも頑張ります! さて、先日卒業生からこんなお悩みメールが届きました。 今ちょうど1つ悩んでまして… 販売の半分以上を締めるあるお取引先さまの支...

.png)
